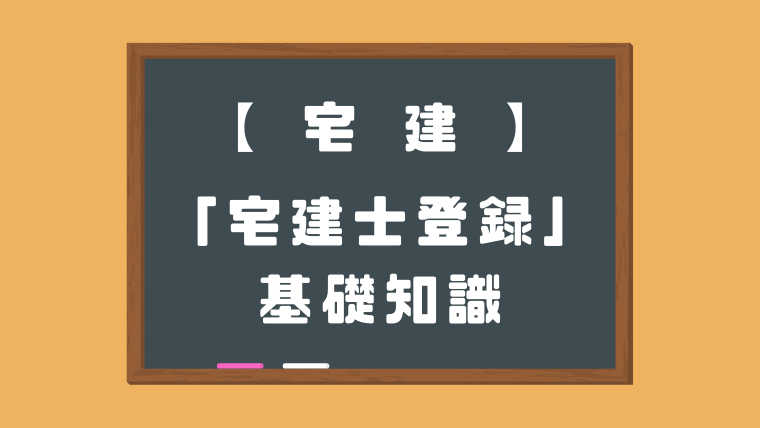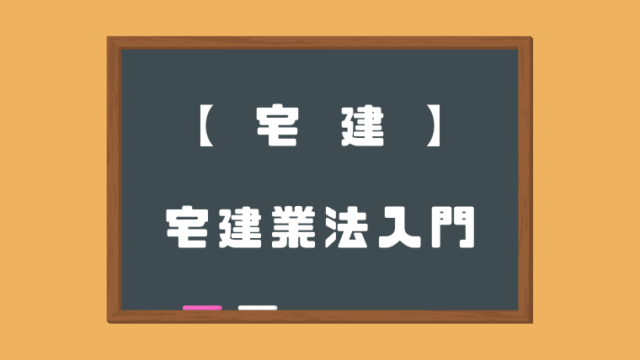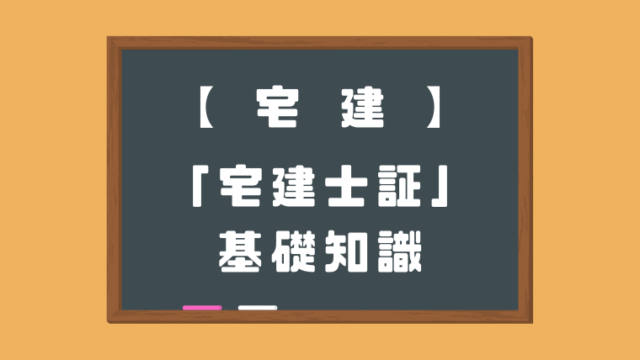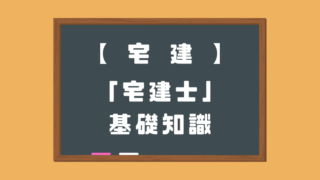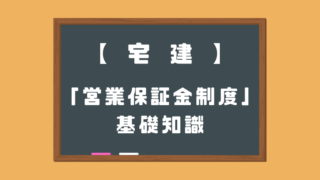こちらでは「宅建士登録」に関する基礎知識として、以下の4つについて説明します。
- 登録の基準
- 登録の移転
- 変更の登録
- 登録の効力
さっそく、「登録の基準」から始めましょう!
Contents
登録の基準
「登録の基準」とは?
「登録の基準」とは宅建士登録を受けるために満たさなければならない条件のことです。具体的には、以下の3つの基準をいいます。
① 宅建試験に合格していること
② 登録の欠格要件にあたらないこと
③ 実務経験がある又は一定の能力が認められること
宅建士登録を受けるためには、この3つの条件をすべて満たしたうえで、「登録の申請」をする必要があるわけです。
①については、特に説明の必要はないと思いますが、②③については、もう少し詳しく説明しておきたいと思います。
登録の基準2「登録の欠格要件にあたらないこと」
まずは、「登録の欠格要件にあたらないこと」についてです。
「登録の欠格要件」とは宅建士登録を受けるのにふさわしくない人の条件のことです。例えば、宅建業法は「暴力団員であること」を登録の欠格要件として定めています。
暴力団員はいわゆる反社会的勢力ですから、宅建士登録を受けるのにふさわしくない人であるといえます。だからこそ、宅建業法は「暴力団員であること」を登録の欠格要件として定め、宅建士登録を受けられないようにしています。
このように、登録の欠格要件には、「宅建士として仕事をさせるには問題がある人の宅建士登録を受けられないようにする」という優れた機能があります。
宅建業法が定める「登録の欠格要件」には、他にも以下のようなものがあります。
・暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
・破産者で復権を得ない者
まだまだたくさんありますが、それらについては各自のテキスト等を確認してみて下さい。
基本的には、「免許の欠格要件と同じものが多い」というイメージで押さえておけばOKです。要するに、「宅建業の免許をもらえない人は、宅建士登録も認められない」ということです。
登録の基準3「実務経験がある又は一定の能力が認められること」
続いては、「実務経験がある又は一定の能力が認められること」について説明します。
この基準の具体的な意味は以下の通りです。
- 宅建取引についての実務経験が2年以上あること
- 国土交通大臣が宅建取引についての実務経験が2年以上ある者と同等以上の能力を有すると認める者であること
簡単に言えば、①は「宅建士登録には不動産屋で2年以上働いていた経験が必要である」ということです。
また、②に「国土交通大臣が宅建取引についての実務経験が2年以上ある者と同等以上の能力を有すると認める者」とありますが、具体例は「国土交通大臣の登録を受けた講習(登録実務講習)を修了した者」です。
つまり、不動産屋で2年以上働いた経験がない宅建試験の合格者でも、この「登録実務講習」を修了すれば、宅建士登録を受けることができるということです。
簡単にまとめると、「不動産屋で2年以上働いた経験がある」か「登録実務講習を修了する」かのどちらかを満たせば、「実務経験がある又は一定の能力が認められること」という基準をみたすということです。
「登録の基準」に関する説明は以上です。
登録の移転
続いて紹介する宅建士登録に関する基礎知識は「登録の移転」です。
「登録の移転」とは自分の宅建士登録における登録先を変更することを言います。例えば、甲県知事の宅建士登録を受けているAが、登録先を甲県知事から乙県知事に変えることを言います。
「登録の移転」はそれまでと別の都道府県にある宅建業者の事務所で働くことになった場合にすることが出来ます。
例えば、甲県知事の宅建士登録を受けている宅建士Aが甲県内にある宅建業者Bの事務所で働いているとします。その後、Aが宅建業者Bの乙県の事務所に転勤となった場合、Aは甲県知事の登録から乙県知事の登録へと「登録の移転」をすることができます。
「登録の移転」の注意点
以上が「登録の移転」についての基本的な説明になりますが、注意点が2つあります。
一つは、「登録の移転は義務ではない」ということです。つまり、「しなければならない」ものではなく、あくまで「することができる」ものに過ぎないということです。先の具体例のように、都道府県をまたいで宅建士の勤務先が変わった場合に「登録の移転」をしないことも許されます。
もう一つは「勤務先の変更を伴わない単なる住所変更の場合にはできない」という点です。例えば、東京都知事の宅建士登録を受けているAが神奈川県に引越しをして住所が変わったとしても、それだけでは「登録の移転」をすることはできません。
「登録の移転」に関する基礎知識の説明は以上です。
変更の登録
続いては、「変更の登録」について、説明します。
「変更の登録」とは宅建士資格登録簿の登載事項に変更があった場合に、その内容を書き換えてもらうことをいいます。
例えば、甲県知事の登録を受けている宅建士Aが引越しによって住所が変わったとします。この場合、Aは登録先の都道府県知事に申請して、宅建士登録簿の記載を旧住所から新住所に書き換えてもらう必要があります。これが「変更の登録」です。
上記のような「住所」だけでなく、氏名、本籍、勤務先の宅建業者の名称に変更があった場合など「変更の登録」が必要な場合は、他にも色々あります。各自テキスト等で確認してみてください。
「変更の登録」に関する基礎知識は以上です。
登録の効力
続いては、「宅建士登録の効力」について説明します。
「宅建士登録の有効期間はいつまでか?」という「時間的効力」と「宅建士登録の効力が及ぶエリアはどこまでか?」という「場所的効力」に分けて説明しましょう。
時間的効力
まず、時間的効力ですが、実は宅建士登録には有効期間がありません。すなわち、宅建士登録は一度すれば、一生有効です。
もっとも、「登録消除処分」によって、宅建士登録が取り消されてしまうことがある点には注意しましょう。「登録消除処分」とは宅建士登録を受けている者が一定の悪いことをした場合に、都道府県知事がその登録を取り消してしまう処分(登録抹消処分)のことです。
場所的効力
また、場所的な効力ですが、これは日本全国に及びます。すなわち、宅建士登録を受けている者は登録先の都道府県のみならず、日本全国で宅建士としての仕事ができます。
例えば、宮城県知事の宅建士登録を受けているAが宅建士として仕事をする場合、宮城県内だけではなく、日本全国で宅建士として仕事ができるということです。
まとめ
「宅建士登録」に関する基礎知識は以上となります。ここで説明した基本知識を前提として、各自のテキストで細かい部分を押さえてみてください。
それでは今日はここまでとします。お疲れさまでした。