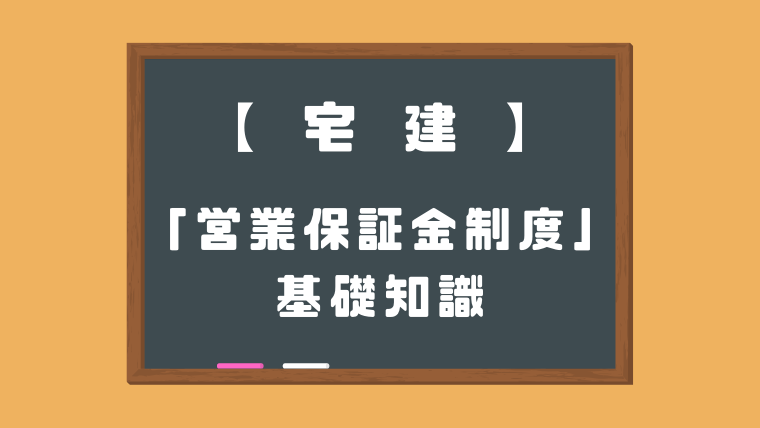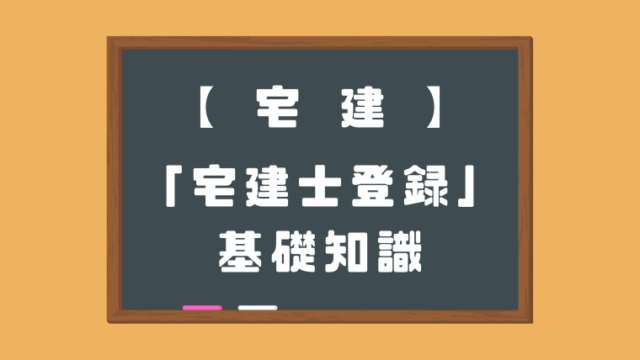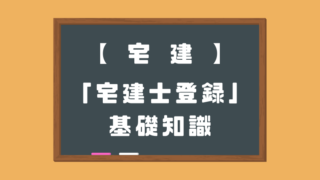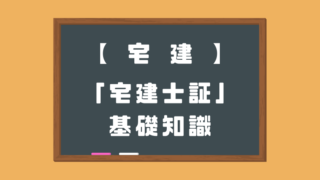こちらでは「営業保証金制度」に関する基礎知識として、以下の項目について説明していきます。
- 営業保証金制度とは?
- 営業保証金の額・供託場所等
- 営業保証金の還付
- 営業保証金の取戻し
- 保管替え
さっそく、「営業保証金制度とは?」から始めましょう!
Contents
営業保証金制度とは?
「営業保証金制度」とは新たに宅建業を営もうとする宅建業者は営業保証金を供託しなければならないという制度のことです。
上記の説明の中に出てくる「営業保証金」や「供託」についても簡単に説明しておきましょう。
「営業保証金」とは宅建業を営むのに必要な保証金(もしものときに備えて用意しておかなければならないお金)のことです。
詳しくは後ほど説明しますが、営業保証金は「損害賠償が支払われない」「手付金が返還されない」など、宅建業者から支払われるべきお金を支払ってもらえないお客さんを救済するために使われます。
また、「供託」とは供託所にお金を預けることをいいます。
「供託所」とは供託事務を行う国家機関であり、具体的には法務局、地方法務局及び支局を指します。とりあえず、「供託所=法務局」「供託所=宅建業者が営業保証金を預けておく場所」との認識でOKです。
もう少し具体的について説明します。以下の事例を見て下さい。
宅建業者Aが仕事上ミスをして、お客さんBに700万円の損害を与えてしまった。BはAに対して、700万円の損害賠償の支払いを求めたが、Aはこれに応じない。このような場合、Bはどうすればよいか?なお、Aは宅建業を始めるにあたって、営業保証金1000万円を甲供託所に供託している。
宅建業者が仕事上ミスをしてお客さんに損害を与えてしまった場合、宅建業者はお客さんに損害賠償を支払う必要があります。
「損害賠償」に関する詳細は、民法の「債務不履行」や「不法行為」で勉強します。今は深入りせずに、とりあえず「そういうものなんだ」となんとなく理解しておけばOKです。
今回の事例も「損害賠償」の事例ですが、要するに「宅建業者Aがお客さんBに対して支払わなければならないはずの損害賠償700万円を支払わない」という事例です。
このように、宅建業者がお客さんに対して支払うべきお金を支払わない場合、お客さんはどのような手段で宅建業者からお金を回収することができるのでしょうか?
一つは、「裁判所の力を借りる」という方法が考えられます。
今回の事例でいえば、BがAを相手に裁判を起こし、Aの財産に強制執行をかけるなどの手段を使って、Aから700万円を回収するというものです。
しかし、この方法は手続きが難しく、解決までに時間やお金もかかりますから、一般的な宅建業者のお客さんが簡単に行えるものではありません。
そこで、登場するのが「営業保証金制度」です。これを利用すれば、お客さんは「宅建業者が払うべきお金をちゃんと払ってくれない」という非常事態にも、比較的簡単に対処することができます。
すなわち、宅建業者がお客さんに支払うべきお金を支払わない場合、お客さんは宅建業者が供託所に供託した営業保証金から、必要なお金を引っ張ってくることができます。(これを「営業保証金の還付」といいますが、詳細は後ほど説明します)。
今回の事例でいうと、BはAが宅建業を始めるにあたって、甲供託所に供託した営業保証金1000万円から、損害賠償額にあたる700万円を受け取ることができます。簡単に言えば、Bは甲供託所に対して、「Aが700万円を支払ってくれないので、Aの営業保証金から700万円を受け取りたいです」という請求(これを「還付請求」といいます)をすることで、Aの営業保証金から、損害賠償700万円の支払いを受けることができます。
このように、宅建業法が「営業保証金制度」を定めているおかげで、宅建業者がちゃんとお金を支払ってくれない場合でも、お客さんは比較的簡単にそのお金を回収することができる仕組みになっています。
宅建業法は「お客さんを守るためのルール」を定める法律ですが、「営業保証金制度」もまさにこうしたルールの一つというわけです。
以上が「営業保証金制度」の簡単な説明です。
営業保証金の額・供託場所等
「営業保証金制度」のイメージをつかむことができたら、次は営業保証金制度に関する様々な基礎知識について勉強していきましょう。
まずは、「営業保証金の額」についてです。
営業保証金の額
先ほど説明した通り、宅建業者は宅建業を始めるにあたって、営業保証金を供託しなければなりません(25条1項)。では、宅建業者が供託しなければならない営業保証金の額はいくらなのでしょうか?
この点については、以下のようなルールとなっています。
宅建業者は以下の営業保証金を供託しなければならない。
主たる事務所(本店)の分 → 1000万円
その他の事務所(支店)の分 → 1つにつき500万円
上記のように、営業保証金の額は宅建業者の事務所の数によって決まります。まず、宅建業者の事務所が一つだけ、すなわち、本店だけの場合は営業保証金の額は1,000万円となります。また、本店だけでなく、支店もある宅建業者の場合、営業保証金の額は本店の1,000万円に加えて、支店1つにつき500万円が加算されます。
例えば、宅建業者Aが本店のほか、2つの支店を設置して宅建業を営もうとする場合、供託しなければならない営業保証金の額は1000万円+(500万円×2)=2000万円となります。
ちなみに、事務所の数が増えると営業保証金の額が増える理由は、事務所が多い宅建業者はお客さんの数も多いので、もしもの時にお客さんを守るためのお金である営業保証金も多く必要だからです。
有価証券による供託
営業保証金の額は最低でも1,000万円と高額です。営業保証金はもしもの時にお客さんを守るためのお金なので、安くするわけにはいきませんが、これを用意しなければならない宅建業者にとっては大きな負担となります。
こうした事情から、宅建業法は「現金」だけでなく、「一定の有価証券」による供託も認めることで、営業保証金の供託をしやすくしています。
簡単に言うと、「有価証券」とは財産的な価値があるチケットのことです。「財産的な価値がある」というのは、「お金に換えることができる」というイメージでOKです。
なお、有価証券で営業保証金の供託をする場合、その種類によって評価額(現金で供託した場合と比較したレート)が異なるので注意してください。具体的には以下の通りです。
| 有価証券の種類 | 評価額 |
| 国債証券 | 額面金額 |
| 地方債証券・政府保証債証券 | 額面金額の90% |
| その他法令で定める有価証券 | 額面金額の80% |
例えば、額面金額が1000万円の地方債証券で営業保証金の供託を行った場合、その評価額は1000万円×90%=900万円となります。仮に、供託すべき営業保証金の額が1000万円であるとすると、営業保証金の額が100万円足りないことになります。この場合、残りは現金等で供託する必要があります。
営業保証金の供託場所
次に、「営業保証金の供託場所」について説明します。先ほど、宅建業者が営業保証金を供託すべき場所は「供託所」であると説明しましたが、供託所は全国各地にたくさんあります。
では、宅建業者はいったいどの供託所に営業保証金を供託すればよいのでしょうか?こうした「営業保証金を供託すべき場所」について、宅建業法は以下のようなルールを定めています。
営業保証金は主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
上記の通り、営業保証金の供託場所は「宅建業者の主たる事務所の最寄りの供託所」となります。すなわち、宅建業者は本店に一番近い供託所に営業保証金の供託を行わなければなりません。
例えば、宅建業者Aの本店が仙台市にある場合、Aは仙台の供託所(仙台法務局)に営業保証金を供託しなければならないということです。
供託場所の注意点として、押さえておいて欲しいのは「支店分の営業保証金も本店最寄りの供託所にまとめて供託をしなければならない」ということです。支店分の営業保証金は支店の最寄りの供託所に供託するのではありません。
例えば、仙台市に本店、山形市に支店が1つある宅建業者Aが営業保証金の供託を行う場合を考えてみましょう。この場合、営業保証金の額は本店分1000万円と支店分500万円の合計1500万円となりますが、その全額を供託すべき供託所は仙台の供託所(仙台法務局)になります。
支店分の営業保証金500万円は支店の最寄りの供託所である山形の供託所(山形地方法務局)に供託するのではありませんので注意してください。
供託後の届出
続いては、「営業保証金を供託した後に必要となる手続き」について説明します。以下の条文を見て下さい。
宅地建物取引業者は、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
このように、営業保証金の供託をしたら、宅建業者は免許権者である国土交通大臣又は都道府県知事に対して営業保証金の供託をした旨の届出をしなければなりません。
さらに言うと、宅建業者はこの届出をしてはじめて、宅建業を開始できるというルールになっています。営業保証金を供託しても、それについての届出をしないまま宅建業を開始することは宅建業法違反となりますので、注意しましょう。
また、宅建業法は免許権者に対しても義務を課しています。その内容は以下の通りです。
国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許(宅建業の免許)をした日から三月以内に宅地建物取引業者が第四項の規定による届出(営業保証金の供託をした旨の届出)をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならない。
簡単に言うと、宅建業者に免許を与えた国土交通大臣・都道府県知事は営業保証金の供託をしたという届出をしない宅建業者に対して、「早く届出をしなさい」と促さなければならないということです。
「催告」とは相手に対して一定の行為を要求することを言います。ここでは、免許権者が宅建業者に対して、「営業保証金を供託した旨の届出をしてね」と催促することを意味します。
なお、免許権者の催告が宅建業者に到達した日から1か月以内に宅建業者が営業保証金を供託した旨の届出をしない場合、免許権者は宅建業者の免許を取り消すことができます(25条7項)。
営業保証金の還付
続いて、「営業保証金の還付」について説明します。
「営業保証金の還付」とは宅建業者からお金を支払ってもらえないお客さんが営業保証金から必要なお金を引っ張ってくることをいいます。
冒頭の事例でいうと、宅建業者Aから700万円の損害賠償を払ってもらえないお客さんBが、甲供託所にあるAの営業保証金から700万円を受け取ることが「営業保証金の還付」にあたります。
還付を受けられる者
宅建業者からちゃんとお金を支払ってもらえない者は誰でも営業保証金の還付を受けられるわけではありません。還付を受けられる者は一定の者に限られます。具体的には以下の通りです。
宅建業者と宅建業に関し取引をした者で、その取引により生じた債権を有する者(宅建業者であるものを除く)
「債権」とは特定の人に対して「~してくれ」と請求できる権利のことを言います。とりあえず、「債権=『金を払え』と言える権利」であると理解しておけばOKです。
簡単に言うと、還付を受けられるのは、宅建業者から払うべきお金を払ってもらえない「宅建業者のお客さん」だけです。
宅建業者と取引をした者であっても、例えば、①広告代金を払ってもらえない広告業者や②宅建業者から給料を払ってもらえない宅建業者の従業員などは営業保証金の還付を受けることはできません。
これらの者は宅建業者と「宅建業に関し取引をした者」ではないからです。営業保証金制度はあくまでも、宅建業者の一般のお客さんを守るための制度なので、一般のお客さんではない者は保護の対象には含まれないのです。
なお、営業保証金の還付を受けるには、供託所にその旨の請求をする必要があります。すなわち、還付を受けたい人は供託所に対して、「私は還付を受けたいのでお願いします」と申し出る必要があるということです。
還付上限額
続いては、「還付上限額」に関する説明です。これは、「宅建業者にお金を払ってもらえないお客さんは、最高でいくらまで営業保証金からお金を引っ張ってくることができるか?」という問題です。
宅建業法は「還付上限額」について以下のように定めています。
還付上限額 = 供託された営業保証金の額
上記の通り、お客さんは宅建業者が供託した営業保証金の額を上限として、営業保証金の還付を受けることができます。
例えば、宅建業者Aが2000万円を営業保証金として供託している場合、そのお客さんBが受けられる還付上限額は2000万円となります。
冒頭の事例では、BはAが支払わない700万円全額について営業保証金から還付を受けることができます。しかし、仮にAの損害賠償額が2500万円だった場合、Bは2000万円は営業保証金から還付を受けられますが、残りの500万円は別の方法で回収する必要があります。
不足額供託
次は、「不足額供託」について簡単に説明します。まずは、「不足額供託」がどんなものなのかをざっくりと理解してください。
営業保証金の還付によって、供託すべき営業保証金の額に不足が生じた場合、宅建業者はそれを補充するための供託をしなければなりません。
例えば、供託すべき営業保証金の額が1000万円である宅建業者Aのお客さんBが600万円の還付を受けた場合、Aの営業保証金は残り400万円となり、600万円の不足が生じます。この不足を補うために、Aは新たに600万円を供託をしなければなりません。
これが「不足額供託」です。
なお、不足額供託は免許権者から「不足額供託をしてくださいよ」という通知を受けた日から2週間以内にしなければならないとされています。また、この通知を受けて不足額供託をした宅建業者はその日から2週間以内に免許権者に「不足額供託をした」旨の届出をしなければならないとされています。
営業保証金の取戻し
続いては、「営業保証金の取戻し」について説明します。
「営業保証金の取戻し」とは宅建業者が供託所に供託している営業保証金を自分のもとに引き上げることを言います。
例えば、1000万円の営業保証金を供託している宅建業者Aが供託先である甲供託所から、営業保証金1000万円を返してもらうことをいいます。
取戻事由
では、宅建業者はどのような場合に、営業保証金を取り戻すことができるのでしょうか?
宅建業者が供託をした営業保証金を取り戻すことができるのは一定の場合に限られます。この一定の場合を「取戻事由」と言います。宅建業法はいくつかの「取戻事由」を定めていますが、分かりやすいものは以下の通りです。
- 宅建業者の免許の有効期間が満了したとき
- 宅建業者の免許が取り消されたとき
- 宅建業者が廃業届を出したとき
上記を一言でまとめると、「宅建業者が宅建業をやめる場合に営業保証金の取戻しができる」ということになります。
なお、上記以外にも取戻事由はありますので、各自のテキスト等で確認してみてください。
取戻し前の「公告」
もう一つ、「営業保証金の取戻しには原則として『公告』が必要である」という点について説明しておきます。
「公告」とは宅建業者が営業保証金の還付を受ける権利を有する者に対して、一定期間内に申し出るよう広く呼びかけることを言います。
簡単に言えば、宅建業者が「営業保証金を引き上げてしまうので、還付を受けたい人は早く申し出てください」と呼びかける手続きが「公告」手続きになります。
営業保証金を取り戻すのに、こうした広告手続が必要な理由は、「お客さんに還付をうけるチャンスを与えてあげる」という点にあります。
宅建業者が営業保証金を取り戻してしまうと、お客さんはもはや還付を受けられなくなってしまいます。還付を受けたいお客さんがこうした不利益を受けないようにするための手続きが「公告」であるということです。
なお、今回は入門段階なので説明を省略しますが、「公告なしに営業保証金の取戻しができる」というケースもあります。このあたりは、各自のテキストで確認してみてください。
保管替え
最後に、「保管替え」について説明します。
「保管替え」とは?
宅建業者が本店を移転した結果、営業保証金の供託場所である「主たる事務所(本店)の最寄りの供託所」が変わることがあります。このような場合に、宅建業者の営業保証金をそれまでの供託場所である供託所から新たに本店最寄りの供託所となった供託所に移すことを「保管替え」といいます。
例えば、宅建業者Aが本店を仙台市から横浜市に移転した場合に、その営業保証金の供託先を従来の本店最寄りの供託所である仙台の供託所(仙台法務局)から、新たに本店最寄りの供託所となった横浜の供託所(横浜地方法務局)に移すというケースです。
こうした「保管替え」は、従来の供託所に対して「保管替えの請求」をすることで行います。簡単に言えば、「保管替えの請求」とは宅建業者が従来の供託所に対して、「本店の移転によって、本店最寄りの供託所が○○に変わったので、営業保証金をそっちに移してください」と請求することを意味します。
「保管替え」の注意点
以上が「保管替え」に関する基本的な説明となりますが、「保管替え」に関して一つ注意点があります。
それは、「保管替え」は現金のみで営業保証金の供託をしている場合にだけ可能であるということです。すなわち、営業保証金の供託を①有価証券のみで行っている場合や②現金と有価証券の両方で行っている場合は「保管替え」はできません。
これらの場合は、いったん新しい本店最寄りの供託所に営業保証金の供託をしたあと、それまでの本店最寄りの供託所から営業保証金の取戻しをする必要がありますので、注意しましょう。
まとめ
「営業保証金制度」に関する基礎知識の説明は以上です。
「営業保証金制度」とセットで勉強して欲しいテーマとして「保証協会制度」があります。余裕のある方は、引き続き勉強してみてください。
今日はここまでとします。お疲れさまでした。