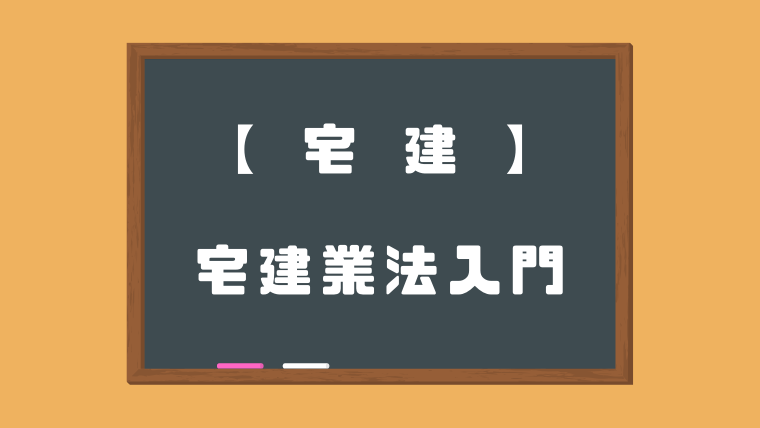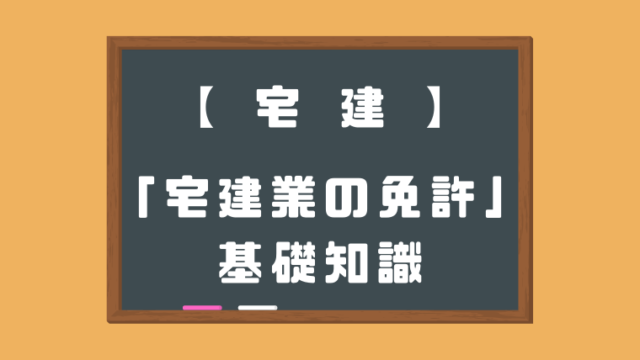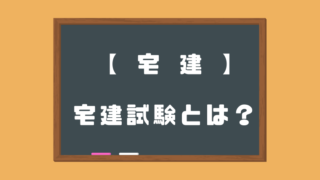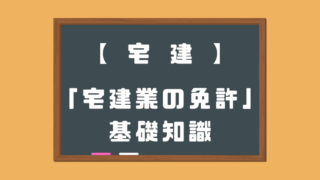こちらの記事では、宅建業法を初めて学ぶ人向けに「宅建業法がどのような法律であるか?」「宅建業とは何か?」について解説していきます。
Contents
「宅建業法」とは?
まずは、ざっくりと説明します。宅建業法とは「宅建業」に関するルールを定めた法律です。
簡単に言えば、宅建業とは不動産業のことです。不動産業にもいろいろありますが、ここでは、お客さんの不動産取引をサポートしてあげることで報酬をもらったり、不動産の転売により利益を得たりする商売のことだと考えてください。
そして、こうした不動産業を営む上で守らなければならないルールを定めているのが、「宅建業法」です。
「宅建業法」は何のためにあるのか?
それでは、宅建業法は何のためにあるのでしょうか?簡単に言えば、「宅建業のお客さんを守るため」です。
もし、宅建業法がなければ、どうなるでしょうか?
これは「宅建業に関するルールが存在しない」ということを意味しますので、宅建業者の中には、とにかく自分が利益だけを考え、お客さんに粗悪な不動産を売りつけるなどの悪い行いをする業者も出てきてしまうでしょう。
こうした事態を避けるためには、宅建業を営む上でのルールを決めて、それを業者に守らせることが有効です。だからこそ、宅建業法はそのようなルールを定めているのです。
宅建業法は「悪徳宅建業者からお客さんを守ってくれる頼もしい存在である」といえます。
「宅建業」とは?
続いて、「宅建業」について、もう少し詳しく説明しましょう。
先ほどの説明では、「宅建業=不動産業」という大雑把な説明をしましたが、正確に言うと、宅建業と不動産業はイコールではありません。
例えば、いわゆる「アパート経営(アパートを所有し、それを人に貸すことで賃料収入を得ること)」は一般的には不動産業に含まれますが、宅建業ではありません。
では、いったい「宅建業」とはどのようなものをいうでしょうか?
結論から言うと、以下の通りです。
宅建業 = 宅地又は建物の取引を業として行うこと
この定義のポイントは、その中に登場する「宅地」「建物」「取引」「業」という4つの言葉の意味を正確に理解することにあります。
さっそく、それぞれの意味について説明しましょう。
「宅地」とは?
まずは、「宅地」についての説明です。簡単に言えば、「宅地」とは①建物が建てられている土地か②建物を建てる予定の土地のことです。
とりあえずはカンタンに「『住宅などの建物を建てるための土地』だから『宅地』である」と理解しておきましょう。
なお、「宅地」の正確な意味は以下の通りです。
・建物の敷地に供せられる土地
・用途地域内の土地で道路・公園・河川・広場・水路以外の土地
上記の中に登場する「用途地域」という言葉は、都市計画法で勉強しますので、入門段階ではあまり気にしなくてもOKです。
「建物」とは?
次に、「建物」についてですが、これは、普通の意味で理解すればOKです。すなわち、家やビル、倉庫など「土地に建てられた物」が「建物」であるという理解です。
「業」とは?
続いては「業」についての説明です。先ほど述べた通り、宅建業とは宅地又は建物の取引を「業」として行うことを言いますが、ここでいう「業」とは①不特定多数の者に対して、②反復継続して行うことを意味します。
簡単に言えば、「いろんな人を相手に、繰り返し何度もやること」が「業」です。「商売としてやる=業」というイメージで理解しましょう。
つまり、宅建業とは宅地や建物の取引を「①不特定多数の者を相手に②反復継続して行うこと」であるということになります。
注意点は、①不特定多数の者を相手にしない場合(特定の者だけを相手にする場合)や②反復継続して行わない場合(繰り返し行うわけではない場合)は「業」にはあたらないということです。
例えば、「マイホームの購入」や「親から相続した宅地を売却処分すること」は、宅地や建物の取引を「不特定多数の者を相手に反復継続して行う」わけではないので、宅建「業」にはあたりません。
「取引」とは?
最後に「取引」について説明します。ここでいう「取引」は以下の3つのことです。
① 自ら売買・交換を行うこと
② 他人の売買・交換・貸借を代理すること
③ 他人の売買・交換・貸借を媒介すること
これだけだと分かりづらいと思いますので、順番にもう少し詳しく説明していきましょう。
まず、①の意味ですが、これは「自分が当事者となって売買や交換を行うことは『取引』にあたる」ということを意味します。
「売買」「交換」とは?
「売買」とはお金と物を交換する契約のことです。例えば、Aが自己所有の甲土地を1000万円でBに売却する場合にAB間で結ばれる契約が「売買」です。この例は「不動産の売買」ですが、スーパーやコンビニでする買い物なども「売買」です。
では、「交換」とは何でしょうか?「交換」とは物と物を交換する契約のことをいいます。例えば、Aが所有する甲土地とBが所有する乙土地を交換し、乙土地をAの所有、甲土地をBの所有とすることです。
以上から、「自分が当事者となって売買や交換を行うことは『取引』にあたる」ということの意味は理解できたと思います。
続いて②と③の意味ですが、これは「他人の売買・交換・貸借を代理又は媒介することは『取引』にあたる」ということを意味します。
これを理解するためには「貸借」「代理」「媒介」の意味を理解する必要がありますので、この点について説明していきましょう。
「貸借」とは?
まずは、「貸借」ですが、これは物を貸し借りする契約のことです。具体例は、Aが甲建物を月10万円でBに貸してあげるような場合です。AB間で「甲建物」という「物」が貸し借りされているので、「貸借」になります。
また、こちらの例では、借主であるBがAから建物を借りている間、毎月「10万円」というお金(賃料)を対価として払わなければならないことになっています。このように、物の貸し借りの契約で、借主が対価として貸主にお金(賃料)を払わなければならない契約のことを「賃貸借(賃貸借契約)」といいます。
「貸借」にはいくつかの種類がありますが、中でも「賃貸借」は「貸借」の典型例です。
「代理」とは?
続いて、「代理」について説明します。
「代理」とは他人のために代わりに契約を結んであげることを言います。
「自分の契約は自分で結ぶ」というのが原則ですが、他人が代わりに結んでもOKです。例えば、AがBに甲土地を売却するという場合、AがBとの売買契約を自分で結ぶのではなく、友人のCに頼んで、代わりに売買契約を結んでもらうようなことも認められます。
これが「代理」です。
ちなみに、上記事例のCのように、ある法律行為を他人の代わりにやってあげる人のことを「代理人」と言います。
代理に関する詳細は「民法」で勉強しますので、とりあえずは上の説明を理解してもらえれば大丈夫です。
「媒介」とは?
続いて「媒介」です。
「媒介」とは契約相手を見つけてあげることをいいます。「仲介」と同じです。
こちらも売買契約を例に説明しましょう。以下の事例が「媒介」です。
Aは甲土地を1000万で売却しようと思ったが、自力で買主を見つけることができなかった。そこで、Cに買主探しを依頼し、それを引き受けたCがAのために買主Bを見つけてあげた。その後、AB間で売買契約が結ばれた。
上記の事例では、CがAの契約相手となるBを見つけてあげています。これを「媒介」という言葉で表現すると、「CはAB間の売買契約を媒介した」となります。
宅建業にあたらないもの
以上が宅建業における「取引」の意味についての説明ですが、注意点が一つあります。それは、「自ら貸借は『取引』にあたらない」ということです。
「自ら貸借」とは自分が当事者となって貸借を行うことです。例えば、Aが甲建物をBに月10万円で貸してあげることです。
このような「自ら貸借」は「取引」にはあたりませんので、自分が当事者となって宅地や建物の貸借を業として行っても、それは「宅建業」ではないという点に注意してください。
なお、先ほど説明した通り、貸借を代理・媒介することは「取引」にあたりますので、宅地や建物の貸借の代理・媒介を業として行うことは「宅建業」にあたります。少しややこしい部分ですが、注意してください。
まとめ
少し長くなりましたが、説明は以上となります。宅建業法や宅建業について理解することができましたか?
初めのうちは、宅建業の正確な意味を理解することが難しく感じるかもしれません。しかし、これから本格的に宅建業法の勉強を進めていけば、だんだんと理解が深まってきますので、あまり悩まずにどんどん先に進みましょう!
それでは、今日はここまでとします。お疲れさまでした。